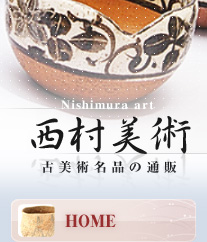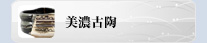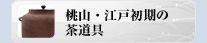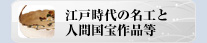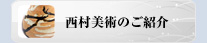|
 |
| タイトル |
| 【第3話】美濃古陶の原点となる志野天目茶碗<白天目)と黄瀬戸天目茶碗について |
美濃古陶といわれる志野・織部・黄瀬戸・瀬戸黒・美濃伊賀・美濃唐津などの茶陶は桃山時代の茶道文化を背景に瀬戸の陶工たちによって生みださたことはよく知られています。産地は瀬戸(愛知県)に隣接する現在の美濃地方〈岐阜県)です。
そして美濃古陶の原点となる茶碗が志野天目茶碗と黄瀬戸天目茶碗です。
江戸時代の書物本朝陶器攻証に文明(1469〜1486)大永(1521〜1527)年間に志野流香道の始祖、志野宗信(1441〜1523)とその子宗温が瀬戸の窯正〈一子相伝を受けた瀬戸の窯集団の窯大将)に(当代第一の名工)加藤宗右衛門春永に命じて茶器を焼くとあり.ます。
志野宗信・宗温は室町幕府に強い影響力をもつ室町末期の大富豪であり香道の始祖でもあり、茶道においても竹野紹鴎の先輩格の先覚者でもあったようです。
また大永3年(1523)志野宗温が白天目茶碗を焼かせたとの記録もあります。
このころ千利休<1522生)の年齢はまだ1歳でした。
一方茶会記の記録を見ますと堺の豪商津田氏が記した天王寺屋会記<天文17年1548からはじまり天正18年1590に終わる)の天文18年伊勢天目茶碗・黄天目茶碗が初めて登場します。
天文22年(1553)同じ茶会記には志野茶碗<白天目茶碗のこと)が初めて登場します。
はっきりした確たる根拠はないのですが昭和になっていろいろ検討された結果この白天目茶碗は現在では唐物(中国産)と推察されています。
しかし文献的には、天文22年以前に日本の瀬戸(美濃)において同じ志野天目が焼かれたことになっています。
白天目とは灰分〈赤松の灰)の含有量を多くした長石を釉薬に用いて還元焼成した天目茶碗で幾分青味のある白い茶碗です。
黄瀬戸天目は長石にさらに灰分を多くした釉薬をかけ酸化焼成をした天目茶碗です。色は落ち着いた黄色(朽葉色)の天目茶碗です。
室町末期の茶道は茶の産地を当てる闘茶の文化でしたがその文化の移行期でした。
そして侘び寂びの茶道文化への移行がはじまっていました。
当時日本の大文化人の頂点に立ち大財閥であった志野宗信・宗温親子2代が強い情熱と莫大な財力を投じ、鎌倉時代からの伝統技術をもつ日本最高の瀬戸名工の力を借りて生み出したのが志野天目<白天目)茶碗であり、黄瀬戸天目茶碗なのです。
世界に誇る抹茶茶碗などの茶器を生み出した桃山時代の美濃古陶は偶然生みだされたのではなく、このような偉大な先人たちの努力の賜物であり、その文化と技術が引き継がれて花が開いたものなのです。
これら天目茶碗は世界の名碗といえる天目茶碗です。志野天目茶碗と黄瀬戸天目茶碗は数碗しか現存しない茶碗です。
そして桃山時代、志野や織部黄瀬戸の名品を生み出した陶工であり窯主こそ、この加藤宗右衛門の子供、、親族でした。美濃の大平窯(加藤景豊)大萱窯(加藤源十郎)九尻元屋敷窯(延加藤景光・景延親子)などによって引き継がれていくのです。
茶会記については時代の記録が正確です。しかし他の書物文献は伝承などの記録も含まれていると思われます。
しかし伝承が含まれるからと言ってすべての内容を否定すべきものではなく参考にすることが大切ではないかと思われます。
美濃古陶は400年前の桃山時代わびさびの茶道文化を背景に生まれましたが、その茶道文化は現在も連綿と受継がれております。
茶道具もまたかなりの数の美濃古陶が伝世品として残されています。いままで未発表の美濃古陶はかなりの数確認されています。
美濃古陶は非常に少ないとはいえ、私自身この35年間に茶碗・鉢・向う付けなどを含めると100点以上の未発表の美濃古陶の伝世品をを確認しています。日本全体ではまだ数千あるいは万単位の美濃古陶の伝世品が残存数しているのではないかと推察されます。
茶道文化が現代生活に息ずくなかで美濃古陶の伝世品の鑑定において文化の途切れた遺跡の鑑定手法である考古学手法による窯跡の物原の限られた資料だけを頼りにした判断基準だけで、それ以外のものを観ることができない不見識な判断基準で美濃古陶の伝せ世品を判断することは大きな問題をはらんでいるように思われます。
(伊勢天目:茶会記に登場しますがどのような天目茶碗か不明です。名前の由来は室町時代、三重県の伊勢の国は美濃の(支配下にある)領国でした。伊勢の地名は有名であり新しい天目茶碗のブランド名として伊勢の名がつけられたものとおもわれます。伊勢産の茶碗でなく美濃産の新作の天目茶碗であると思われます)
第4回骨董談義はこれで終了します。次回をお楽しみに・・・(平成21年1月更新)
西村 克也 |
|
|
COPYRIGHT(C)2006 茶器 古美術 骨董品の西村美術 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|